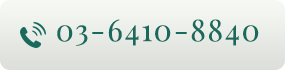タコについて
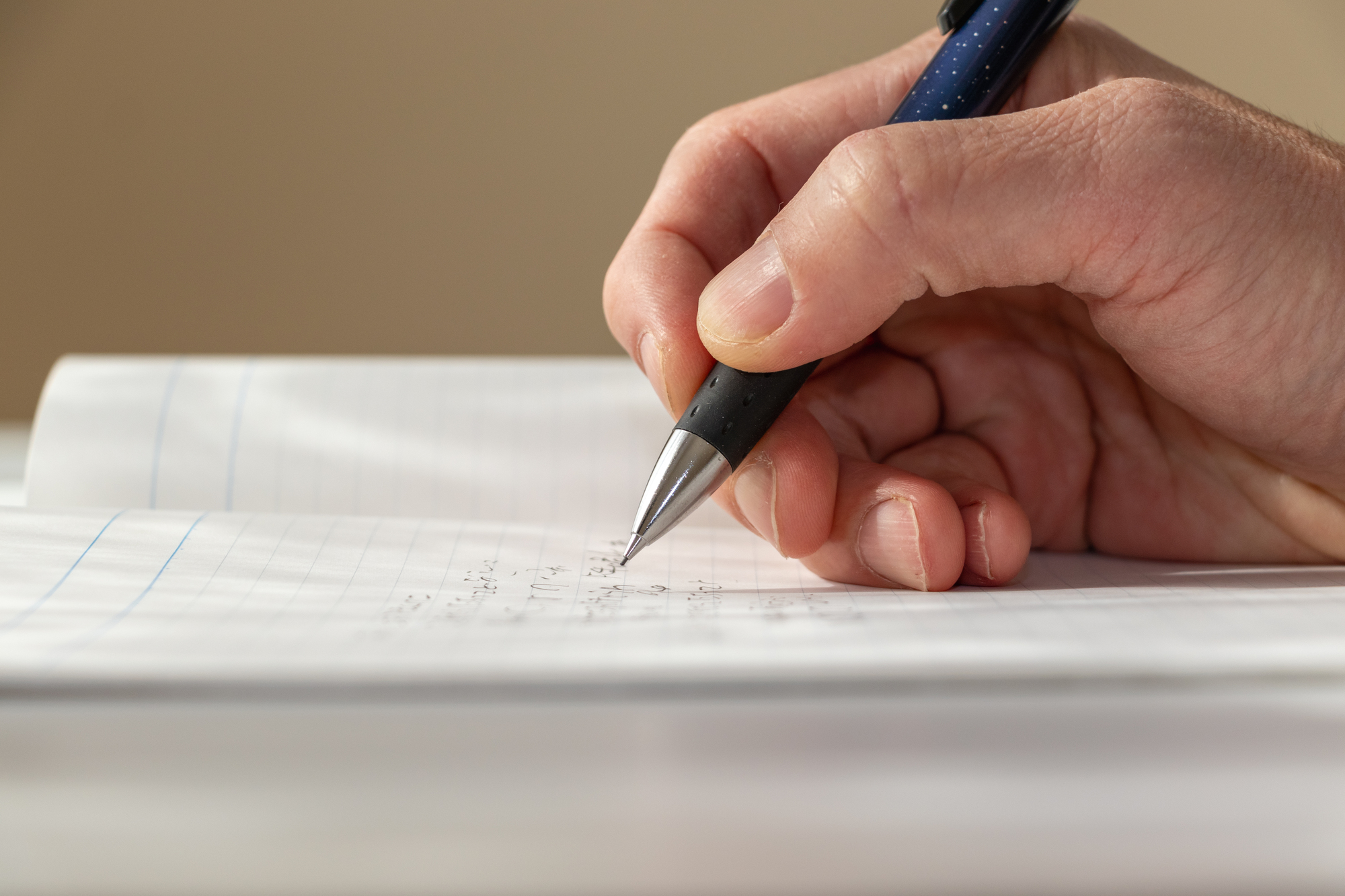 タコは刺激を受けた辺りの皮膚全体がやや黄色がかって厚みと硬さが増し盛り上がることで、専門用語では「胼胝(べんち)」とも呼ばれています。タコは足の裏だけではなく身体のあちこちに生じる可能性があり、ペンダコや座りダコのように生活習慣や癖が影響します。ほとんどの場合痛みはなく、むしろ角質が分厚くなっているため感覚が鈍くなっているというケースもあります。タコに痛みや赤みがある場合は細菌感染が疑われるため、早めに当院までご相談下さい。特に糖尿病を持っている方は、重症になりやすい傾向があるため気を付けるようにしましょう。
タコは刺激を受けた辺りの皮膚全体がやや黄色がかって厚みと硬さが増し盛り上がることで、専門用語では「胼胝(べんち)」とも呼ばれています。タコは足の裏だけではなく身体のあちこちに生じる可能性があり、ペンダコや座りダコのように生活習慣や癖が影響します。ほとんどの場合痛みはなく、むしろ角質が分厚くなっているため感覚が鈍くなっているというケースもあります。タコに痛みや赤みがある場合は細菌感染が疑われるため、早めに当院までご相談下さい。特に糖尿病を持っている方は、重症になりやすい傾向があるため気を付けるようにしましょう。
タコの治療
タコは、必要であれば軟膏などを用いて角質を柔らかくしたり、スピール膏やハサミやメスなどを用いて取り除いたりすることで治療を行います。また、単なるタコではなく、足底粉瘤などの皮下腫瘍が原因で皮膚表面にタコが生じているというケースもあります。そのようなケースでは、まず腫瘍を治療する必要があります。
ウオノメについて
 直径3~7mm程度の硬い皮膚の病変で、成人の足の裏や指などにできることが多いです。名前の由来は病変の中心に見える芯が魚の目のように見えることですが、実は専門用語でウオノメは「鶏眼(けいがん)」と呼ばれています。ウオノメはある特定の部位に異常な圧迫刺激が繰り返し加わることによって生じるもので、タコと違って痛みを伴うことが多いです。厚くなった角質が芯のようにくさび状に真皮に食い込んでいることが原因で、痛みは歩行や圧迫によって引き起こされます。
直径3~7mm程度の硬い皮膚の病変で、成人の足の裏や指などにできることが多いです。名前の由来は病変の中心に見える芯が魚の目のように見えることですが、実は専門用語でウオノメは「鶏眼(けいがん)」と呼ばれています。ウオノメはある特定の部位に異常な圧迫刺激が繰り返し加わることによって生じるもので、タコと違って痛みを伴うことが多いです。厚くなった角質が芯のようにくさび状に真皮に食い込んでいることが原因で、痛みは歩行や圧迫によって引き起こされます。
ウオノメの治療
ウオノメを根本的に治療するためには、ある一部に圧迫などの刺激を繰り返し受けている状況を改善する必要がありますが、ウオノメの場合は歩行時に激しい痛みを伴うため、まずはそれを解消することになります。原因であるくさびのように食い込んだ角質を取り除くために特によく行われるのは、ウオノメの大きさに合わせて切ったスピール膏を数日間貼って角質を柔らかくした後、メスやハサミなどを用いて中心部の真の部分を切り取るという方法です。ドーナツ型パッドを使用して圧迫除去を実施するケースもあり、この方法だと疼痛を軽減し、再発を予防できます。また、電気焼灼法や冷凍凝固療法といったイボ治療と同様の治療を行うこともあります。
タコやウオノメの予防方法
タコやウオノメは、「皮膚の一定の場所への慢性的な刺激」が原因で生じます。「刺激」となるのは窮屈な靴や長時間の歩行、足の変形、歩き方の異常、加齢や病気による脂肪組織の減少の他、浅い場所に骨や関節などの固いものがあるなど様々です。治療と予防の双方の観点から、これらの圧迫因子を特定し、できる限り取り除くことが重要になります。
治療を続けても、この圧迫因子を取り除かない限り治癒は難しく、一度治っても再発が起こりやすくなります。原因が何であっても、靴がその因子に影響していることが多くあります。靴を自分に合ったものへ変えるだけでウオノメが治るケースもあるため、タコやウオノメと診断された際や自覚症状がある場合には一度専門の靴屋さんへ相談してみるのがお勧めです。
ただし、圧迫要因の中には他の疾患や職業上、生活上の習慣など、取り除ききれないものも多くあります。そういった場合は、角質軟化剤や保湿剤でスキンケアを行う、パッドなどで患部への刺激を減らすなどの工夫が大切です。
よくある質問
タコとウオノメの違いは何ですか?
タコとウオノメは、どちらも慢性の刺激によって一部の皮膚の角質層が厚くなる疾患です。タコは刺激を受けた辺りの皮膚全体がやや黄色がかって厚みと硬さが生じる他、ペンダコや座りダコのように生活習慣や職業、癖によって足の裏以外に身体のあちこちに生じるという点でウオノメと異なります。タコはウオノメと違いほとんどの場合痛みを伴わず、むしろ角質が厚くなっているために感覚の鈍麻がみられることもあります。タコに痛みや赤みが生じている場合、細菌感染が疑われますのでお早めに当院までご相談下さい。特に、糖尿病を持っている方は重症になりやすいため注意するようにしましょう。
タコやウオノメの治療は自分で行っても良いですか?
治療を適切に行うためには、まず正しい診断を行う必要があります。イボやウオノメ、タコは良性でよくみられる疾患ですが、区別がつきにくい場合があり、他の皮膚病と混同してしまうこともあります。例として、足の裏にできた悪性腫瘍がウオノメであるとご自身で診断され、自己流の治療を行ううちに進行してしまったというケースも存在します。
また、自己治療によってウオノメを化膿させてしまった糖尿病患者様の例のように、正しい診断が下っていても治療を適切に行わないとむしろ体に害を及ぼしてしまう可能性があります。また、治療の成功のためには、原因となった圧迫要因をできる限り除去する必要があります。治療を行う際はまず皮膚科にかかり、正しい診断を基にした正しい治療が大切です。市販のお薬での自己治療も、医師の指導と管理に基づいて行えば問題ありません。