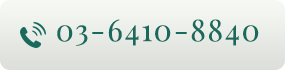多汗症について
 多量の汗によって日常生活に支障が出ている状態を多汗症と言います。日本皮膚科学会の定義によると、原発性局所多汗症とは「温熱や精神的負荷の有無いかんにかかわらず、日常に支障をきたす程の大量の発汗を生じる状態」です。
多量の汗によって日常生活に支障が出ている状態を多汗症と言います。日本皮膚科学会の定義によると、原発性局所多汗症とは「温熱や精神的負荷の有無いかんにかかわらず、日常に支障をきたす程の大量の発汗を生じる状態」です。
多汗症はその原因によって「続発性」と「原発性」の2種類に分けられ、それぞれ直接原因となる疾患がある場合とない場合を指します。
また、発汗のある部位によっても「局所性多汗症」と「全身性多汗症」の2種類に分類されます。腋窩、手の平、足の裏などの発汗が多い場合は局所性多汗症と、全身の発汗が多い場合は全身性多汗症と呼ばれます。発汗の量が増える原因は温熱や疾患に加え、精神状態(緊張など)が影響していることもあります。
多汗症の症状
多汗症の主な症状は全身もしくは脇や手のひら、足の裏、頭皮などの一部に多量の汗をかくことです。
多汗症の原因
多汗症は原因によって2種類に分けられ、そのうち原因が特定できるものを「続発性多汗症(二次性多汗症)」と言います。原因は感染症や神経性疾患、糖尿病、低血糖、内分泌異常といった全身性の疾患や外傷や悪性リンパ腫といった局所的な神経障害など様々です。その他、向精神薬や解熱剤、ステロイドなどの薬の副作用として生じることもあります。
多汗症のうち、発汗量が増加している原因が明確になっていないものを「原発性多汗症」と言います。一説には脳になんらかの異常が起きて交感神経が優位になりやすいことが発汗の原因ではないかとも言われていますが、はっきりと判明はしていません。
原発性局所多汗症の診断
原因が明確でないまま、6ヵ月以上多量の局所的な発汗がみられ、次の6つの症状のうち2つ以上に当てはまる場合、局所性多汗症であると診断されます。
- 25歳以下で最初の症状が発現している
- 発汗は左右で同様にみられる
- 発汗は睡眠中には止まっている
- 多汗だと感じる出来事が、1週間に1回以上ある
- 家族も多汗症の病歴がある
- 汗によって日常生活に支障をきたしている
局所性多汗症が疑われる場合、診断を確定するために発汗検査を実施することがあります。
多汗症の治療
当院では、次のような方法で多汗症の治療を行っております。
保険適用
内服薬
内服薬としては、抗コリン作用で発汗を抑制する効果のある臭化プロバンテリン(商品名:プロバンサイン)を用います。この薬は内服中では汗を抑制しますが、根本的に治療できるわけではなく、内服を止めると発汗も再び始まるため、継続した内服が必要です。臭化プロバンテリンには発汗の抑制の他、唾液の分泌を抑制する効果もみられます。そのため、口渇の症状が強い場合には、内服量を減らすといった対応が必要になります。
塗り薬
オキシブチニン塩酸塩(商品名:アポハイドローション)を使用します。この薬はエクリン汗腺に存在するムスカリン受容体に対して抗コリン作用を有し、それによってアセチルコリンと呼ばれる神経伝達物質の作用が阻害されて発汗が抑制されます。オキシブチニン塩酸塩は、原発性手掌多汗症用の塗り薬としては日本で初めて保険適用が認められた外用の治療薬で、両手の平に就寝前の1日1回適量を塗布します。なお、処方可能な年齢は12歳以上からです。原発性腋窩多汗症に対してもアセチルコリンのムスカリン受容体拮抗薬の外用剤が2種類ありますので、まずはご相談ください。
ボトックス注射
 発汗は、神経伝達物質であるアセチルコリンが神経終末と呼ばれる神経の末端から分泌されて伝達することによって起こります。ボトックス注射を行うと、このアセチルコリンの放出を抑え、過剰な発汗を抑制することが可能です。
発汗は、神経伝達物質であるアセチルコリンが神経終末と呼ばれる神経の末端から分泌されて伝達することによって起こります。ボトックス注射を行うと、このアセチルコリンの放出を抑え、過剰な発汗を抑制することが可能です。
重度の原発性腋窩多汗症の場合、保険適用でこの治療ができます。
保険の適用基準
- 体質的な多汗(原発性多汗症)であり、基礎疾患が原因ではない
- 6カ月以上、過剰な発汗が続いている
- 発汗によって日常生活に頻繁または常に困難が生じている
| 保険適用(3割負担の場合)の料金 | |
| 脇のボトックス注射 | 約33,000円 |
※料金はあくまで目安です。実際は使用する薬剤や部位によって異なります。また、脇以外の部位への施術や、保険適用の基準に満たない場合は保険適用外となります。
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| 脇 | 30,000~70,000円 |
| 手 | 70,000~90,000円 |
| 足 | 80,000~90,000円 |
| 顔 | 40,000~60,000円 |
| 頭 | 80,000~150,000円 |
多汗症の予防
 多汗症には原因がはっきりしないものもあるため一概には言えませんが、生活習慣を改善し、ストレスで交感神経が優位にならないようにすることが予防策として推奨されています。また、辛い食材や酸っぱい食材、カフェインを含むもの(コーヒーなど)といった刺激物、タバコやアルコールなどを控えること、睡眠を十分にとることなどが予防に繋がると言われています。
多汗症には原因がはっきりしないものもあるため一概には言えませんが、生活習慣を改善し、ストレスで交感神経が優位にならないようにすることが予防策として推奨されています。また、辛い食材や酸っぱい食材、カフェインを含むもの(コーヒーなど)といった刺激物、タバコやアルコールなどを控えること、睡眠を十分にとることなどが予防に繋がると言われています。